東北を中心に住宅・建材・リフォーム事業を幅広く展開する株式会社北洲様は、事前点検の効率化と顧客満足度向上を目的に、従来の高所ポールカメラからドローン活用へと移行するためDroneRoofer(ドローンルーファー)を導入。従来の方法では実現できなかった作業効率の向上だけでなく、安全性の大幅な改善や提案力の強化、さらには認知度の向上につなげています。今回、同社のリフォーム事業でドローン導入を推進された小濱 悠暉様に、導入の背景や東北ならではの活用方法、そして得られた成果についてお話を伺いました。
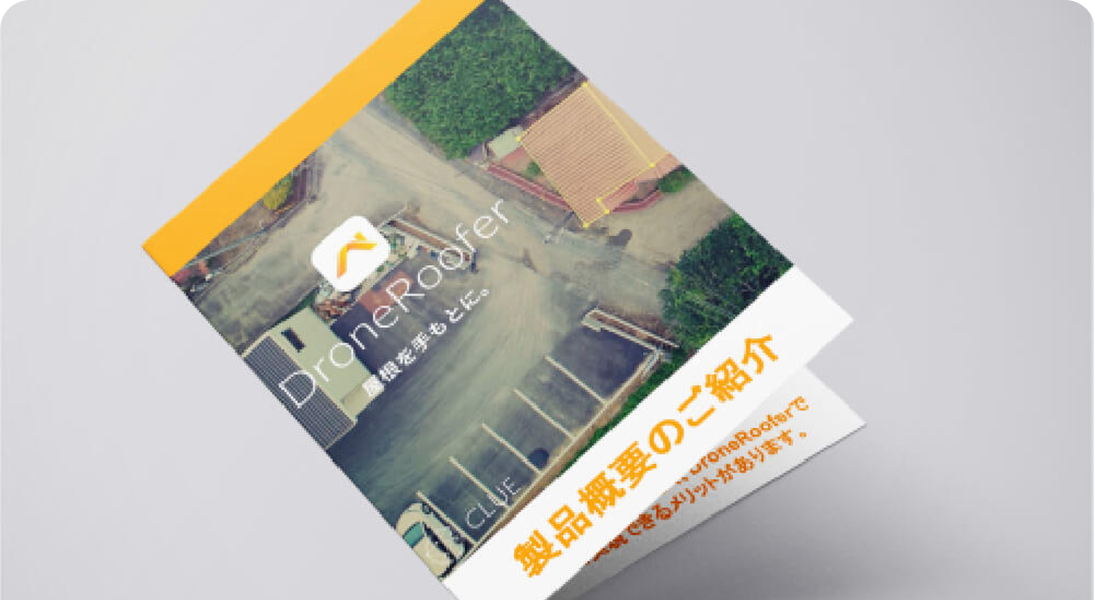
貴社の状況に合う適切な、
DroneRooferの活用方法がわかります。
- ・外装点検を誰でも、安全に実施したい
- ・積算や見積など提案準備を効率化したい
- ・リフォーム提案で他社と差別化したい
目次
東北発、1958年創業の老舗企業が挑む、デジタル変革とダイバーシティ経営
―― 事業概要についてお聞かせください。
小濱様:弊社は1958年に岩手県で創業し、現在は本社がある宮城県を中心に住宅や建材、リフォーム事業を展開しています。近年は北関東にもエリアを広げており、木造の注文住宅の新築、建築資材・建材の供給、そして私が在籍するリフォームまで一気通貫で手がけていることが特徴です。2×6工法や全館空調、省エネ性能に優れたZEBなど、冬の寒さが厳しい東北地方に適した高気密・高断熱の先進的な住まいづくりに注力しており、サステナブルな住環境の提供を目指しています。
弊社のもうひとつの特徴が、女性社長のリーダーシップの下でダイバーシティ経営を進めている点です。設計・施工・営業など幅広い領域で女性社員がマネジメントや実務に参画しており、制度と現場の両輪で、性別や年齢に左右されないオープンな参加機会を設けています。いまだ男性比率の高い住宅、建材、リフォーム業界において、独自のポジションを確立していると考えています。
今回「DroneRoofer」を導入したリフォーム事業は、盛岡・北上・仙台の三拠点合計で年間おおよそ1,700件を扱っており、社内としては取り扱い件数がかなり多い状況です。外装単体の案件はもちろん、スケルトン化を含む大規模なフルリフォーム案件も手掛けています。
―― DXやドローンなど新技術の活用について、どのような姿勢で取り組まれているのでしょうか。
小濱様:社内では早くからIT活用・DXに強い関心を持ち、全社で約1億円規模の投資を行っています。たとえば、施主様へ建築現場の360度写真をVR化した映像を提供したり、クラウドベースの施工管理システムを導入したり、さらに住宅ローンにおいては残価設定型などの新しい金融サービスを提案するなどの取り組みも進めています。
私自身は「社員が幸せに働ける状態をつくる」というミッションのもと、資材発注書式の簡素化といったミクロな内製ツールづくりから着手し、そこから電子受発注の導入、施工管理・発注のクラウド化、工事請負契約の電子契約化などを段階的に進めてきました。その流れで、今回の取り組みである屋根・外壁の事前点検におけるドローン活用を推進しました。現場にデジタルを最適な形で導入することで、「労働集約のしんどさ」を解消しつつ顧客体験を上げることを目指しています。
お客さまの潜在ニーズを引き出し、高付加価値な提案を。信頼構築と業務効率化を同時に追求
―― リフォーム事業における理想像について、どのようなイメージを描いていますか?
小濱様:住宅のリフォームにおけるニーズは極めて多岐にわたり、しかも人生で何度も経験するものではないからこそ、お客さま自身が気づいていない潜在的な要望が埋もれがちです。
それらを丁寧に引き出しつつ、競合他社に埋没しない付加価値を提案できる体制を確立することが理想であり、とくに高単価になりやすい外壁・屋根領域で確かな価値を訴求することが重要だと考えています。お客さまに対しては満足度の高いご提案を、社内に対しては現地調査からプラン作成、提案に至るリードタイムの短縮と、営業・設計・施工の三位一体の連携を滑らかにすることを、同時に実現したいと考えていました。
―― 屋根・外壁の事前点検はどのような業務フローで進めているのでしょうか。
小濱様:営業1名が1日で回れるのは、移動時間を含めると5~6件が限界です。地方ですので移動は車両を基本とし、現地では高所ポールカメラと付属バッテリー、接続用PCを携行して調査を進めます。外装に関わる案件では、屋根の4面を取りこぼしのないように撮影するのですが、そこでこれまで使用してきたのが高所ポールカメラです。
高所ポールカメラはかなり重量があり、体感では約10kg近くもあります。風の影響も受けやすく、伸長時にはかなり不安定です。複雑な屋根形状では細部までは撮影できず、現場の負担、効率性、そして撮影のクオリティといった要素がボトルネックになっていました。
撮影後は画像をPCに取り込み、Excelで点検報告書を整えます。屋根面積は図面や一次情報から推計するのが一般的で、ある程度の経験が必要なために精度のばらつきは避けられませんでした。
—— 高所ポールカメラによる事前点検では、どのような課題があったのでしょうか。
小濱様:大きく3つの課題がありました。第一に作業負荷が重く、調査1件当たり40~50分を要していたことです。加えて、季節・天候の制約を受けやすく、場合によっては50分以上かかってしまうこともありました。2つ目の課題が、高所ポールカメラの画角や解像度の限界から、棟板金のシーリング劣化や天窓の有無などの重要な要素を事前に確定できず、足場設置後に判明して追加契約をお願いせざるを得ないケースが生じていたことです。追加契約は弊社としても本意ではなく、お客さまとの信頼関係に直結する課題です。
そして3つ目に、地域と時期によって事前点検のクオリティ平準化と品質担保が難しいケースが挙げられます。東北では増築を重ねた築年数が古い住宅が多く、屋根形状が複雑化しやすいため、経験の浅い社員にとっては事前点検の難易度が高い物件が多く点在しています。そして北上・盛岡などの積雪地域では、雪解け時期の雨樋点検のニーズが集中するため、どうしても対応できる件数にばらつきが生じていたのです。
高所ポールカメラからドローンへの転換。導入の決め手は、操作性・機能性、サービス設計
—— 「DroneRoofer」をお知りになった当時の状況を教えてください。
小濱様:Facebook広告で屋根点検向けのドローンサービスを見つけたことが出発点です。当時、社内にドローン操縦の経験者はおらず、かくいう私も「使えたらなんか便利そう」程度の認識にとどまっていました。当時は高所ポールカメラによる事前点検が当たり前で特に切迫感はなかった一方、現場の非効率や煩雑さへのフラストレーションは顕在化していました。そこから、まずはドローンサービスの機能と費用感を把握するために比較表づくりから着手し、要件整理と概算予算の目処出しまで一気に進めました。
ただ、ドローンサービスの比較検討については、屋根外装点検に特化したドローン活用サービスは当時「DroneRoofer」以外は見当たりませんでした。測量寄りの近縁ソリューションは存在していたものの、UIや機能が点検分野とは異なると判断し、早々に「DroneRoofer」を中心に検討を進めました。
—— 「DroneRoofer」導入の決め手と、社内意思決定の通り方を教えてください。
小濱様:初心者でも現場で迷わず使える操作性、点検リードタイム短縮に直結する機能性、そして飛行許可申請・保険・各種サポートまでを包括するサービス設計という三点が評価の柱でした。その他にも撮影できる画像の品質やドローンの機能性、つまり狙った場所を撮れるかどうかを確認しています。当初、私が抱いていた印象では、ドローンに取り付けられた小型カメラでは、高所ポールカメラ以上のクオリティで撮影できないのではという先入観があったのですが、実機と実際のサンプル写真を確認してあっさり覆されました。
比較検討を進めていく過程で「外装点検をドローンでDXする」「内装・外装の点検プロセスを段階的にデジタル化する」という意思が担当本部長からも示されたことで決裁はスムーズに進行しました。結果として、社員の負担軽減と効率化を第一に、浮いたリソースを本来価値の高い営業行為へ再配分するという導入意図を掲げて、「DroneRoofer」の導入が決定しています。
導入期に目標を設定し、教育体制を構築。安全運用と自走力の強化で、東北No. 1を目指す
—— 「DroneRoofer」の導入はどのように進行しましたか。
小濱様:導入初期は、CLUE社の担当の方から手厚くサポートいただきました。「何のために飛ばすのか」といったドローン活用の目的と導入フェーズを明確にしていただき、そのうえで定量・定性の両面の目標を一緒に設定し、最終的には「ドローンを扱うリフォーム会社として、東北No. 1の知名度を確立する」というゴールを掲げました。
具体的には、リフォーム案件では原則全件でドローンによる調査を行い、近隣説明を組み込んだ業務フローを三拠点に浸透させること、定量的には1営業日あたり1フライト、3拠点合計で月20~30件のドローン飛行を行うことをストレッチ目標に設定しています。「DroneRoofer」導入から4ヶ月後の時点ですでに合計飛行回数は100件弱と、1営業日あたり1.3フライトとなっていたため、目標を達成することができました。
現在は盛岡・北上・仙台の3拠点に各1機ずつ合計3機を配備しています。導入当初は各拠点に1名ずつドローン活用の旗振り役を配置し、現場の理解浸透や運用ルールの定着をリードさせていましたが、いまでは現場の営業が自走できるレベルに到達したため、専任担当は不要となっています。
—— ドローンによる事前点検では、どのような工夫をしていますか?
小濱様:まずドローン飛行の教育については、本社一括ではなく各事業所のOJTを基本とすることで、各エリアの事情や独自のノウハウを尊重しています。その一方で、安全面については全社統一のルールをいくつか設けています。
たとえば、「ドローン点検中」と書かれた赤ベストの着用義務化や、立て看板の設置で近隣への周知を徹底すること、「慣れたときこそ危ない」という考えからマニュアル操作は禁止とし、タブレットからの自動操作のみと徹底しています。こうした慎重なドローン運用を徹底することで、導入から2年弱が経った現在もドローン事故ゼロを維持できています。
—— 事前点検以外で「DroneRoofer」がお役に立ったケースはありましたか?
小濱様:中古物件を購入し、フルリノベーションを施すことを検討されていたお客さまにご提案したのが、中古物件を購入する前の段階でドローンによる現地調査を行い、物件選びに役立てていただく方法でした。とある案件では、一見好条件の物件だったもののドローンで空から調査してみたところ、棟板金に大きな損傷があったことが判明し、より正確な改修コストを見積もることができたケースがありました。もしドローンを飛ばしていなかったら、リフォーム着手後に多額の追加契約が必要になっていたでしょう。提案の質とブランド信頼に直結する成果につながりました。
また、住宅街でのドローン飛行が近隣住民との接点になったケースもあります。ドローン飛行に興味を持っていただいた近隣住民の方を、完成見学会へ送客できた事例や、近隣へポスティングしたDMにドローン飛行も行っていることを記載したことで、弊社への興味を引くことができています。
雪害点検など、新たな営業接点を創出。高単価案件の受注や、知名度の向上にも貢献
—— 「DroneRoofer」の導入によって、どのような成果が得られていますか?
小濱様:まず点検時間を大きく削減できました。従来の高所ポールカメラで40~50分かかっていた工程が、1フライト10~15分、遅くても20分で完了するようになっています。さらに足場設置後にしか確認できなかった棟板金シーリングの劣化なども、事前に高精細で把握できるようになったため、追加見積もりの後出し感もなくなっています。
また、従来の高所ポールカメラを用いた調査では重さや扱いづらさから身体的な負担が大きく、時には軽いけがにつながるケースもありました。ドローン導入後はそうしたリスクがなくなり、現場からも「もう高所ポールカメラには戻れない」という声が上がっています。新入社員に至っては、そもそも高所ポールカメラを知らない世代となり、業務効率と安全性の両面で大きな変化を実感しています。
—— 「DroneRoofer」の導入が、売り上げ向上に貢献したケースはありましたか?
小濱様:盛岡支店からは、新規顧客や既存顧客向けのイベントで、ご提案のきっかけにドローン無料点検をご案内し、そこから規模の大きいリフォームの受注につながったとの報告がありました。たとえ即時案件化しなくても、ドローンによって接点を増やせたことで顧客との関係性構築に成功しています。外装工事は単価が高い一方でリピート頻度は低いため、こうした顧客接点の創出は重要であり、ドローンが新しい営業ツールとして機能していると言えます。
東北ならではの事例として、春先の雪解けにあわせての雨樋点検にドローンを活用しています。雪の重みで東北の住宅では雨樋の破損が珍しくないのですが、高所ゆえになかなか現状を把握しにくいのです。これも定期的な顧客関係の構築に寄与しており、長期的な売り上げに貢献していると言ってよいでしょう。
また最近では、年始のローカル番組や地元紙に「ドローンを活用するリフォーム会社」として掲載いただいたこともあり、地元からの認知度、好感度の向上に貢献していると思います。
ストーリー設計と現場の積み重ねがカギ。地域プレゼンス強化に向けたドローン活用の展望とは
—— 今後の展望についてお聞かせください。
小濱様:導入時のご担当者と交わした「ドローンを扱うリフォーム会社として、東北No. 1の知名度を確立する」という約束はいまも色褪せていません。事前点検の高度化や提案力の強化という本質を大事にしつつ、ドローンを単なる点検装置ではなく、攻めの訴求ツールとして弊社の価値をお客さまに広く届けていきたいと考えています。
同時に社内では、リフォームにおける各プロセスをデジタルで連携し、サービスの精度向上とリードタイム短縮を両立させる運用をさらに磨き込んでいきたいですね。
—— ドローン導入を検討している読者へ、アドバイスをお願いします。
小濱様:多くのリフォーム事業者が、依然として脚立や高所ポールカメラを使っている現実を踏まえると、まずは現場の安全を見直すべきだと思います。重く不安定な機材を担いで何箇所も撮影していく方法は、現場作業者の負担やヒヤリハットのリスクを抱え続けることになります。
また、ドローン導入の効果を最も強く感じられるのは、営業・設計・施工を一気通貫で回している中小・中堅のリフォーム企業でしょう。現地調査からご提案までのリードタイムを短くしつつ、提案の精度を高めることができれば、それは競合他社との優位性に直結します。
その一方で、ただドローンを購入すれば良いのではありません。ドローンで得られた点検データをいかにご提案に反映していくか、自社ブランドの向上にいかに繋げていくかといった、ドローン導入後のストーリーを明確に描くこと、そして現場の推進役が地道にドローン活用を積み上げていくこと、その両輪が重要です。弊社も引き続き攻めの姿勢のドローン活用を続けていき、東北でのプレゼンスをさらに高めていきたいと考えています。















