リフォーム業界では「営業職の採用と定着」に悩む企業は少なくありません。やっと採用できたと思ったのにすぐに辞めてしまう、成果が出る前に戦力から外れてしまう…そんな悪循環に頭を抱えている経営者や採用担当の方も多いのではないでしょうか。
営業職は、専門的な知識とコミュニケーション力の両方が求められるため、未経験者にはハードルが高く、かといって経験者は採用市場での取り合いが激しいのが現実です。では、どうすれば「長く活躍してくれる営業マン」を採用し、安定した営業体制を築けるのでしょうか?
この記事では、リフォーム営業の採用が難しい理由から、効果的な募集方法、定着につながる育成制度や組織づくりの工夫まで詳しく解説します。さらに、未経験者と経験者を採用する際の戦略の違いや、実際に成果を出した企業の成功事例もご紹介します。
「採用に失敗したくない」「入社した人に長く働いてほしい」——そう感じている方にとって、すぐに活かせるヒントになれば幸いです。
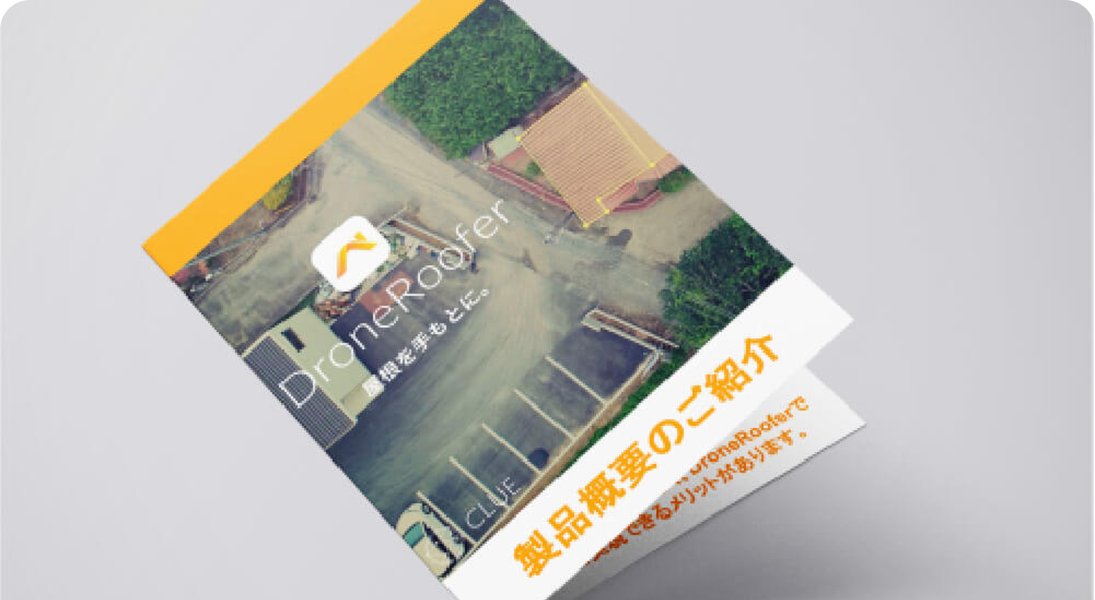
貴社の状況に合う適切な、 DroneRooferの活用方法がわかります。
- ・外装点検を誰でも、安全に実施したい
- ・積算や見積など提案準備を効率化したい
- ・リフォーム提案で他社と差別化したい
目次
なぜリフォーム営業の採用が難しいのか?現場が抱える課題
リフォーム業界では「営業職がなかなか採用できない」「採用してもすぐ辞めてしまう」という声が非常に多く聞かれます。営業職は住宅や建築に関する専門知識が必要なうえ、成果主義のプレッシャーも大きいため、求職者が集まりにくいのが現状です。その結果、せっかく人材を採用しても定着せず、採用コストが無駄になってしまうケースが後を絶ちません。
ここでは、なぜこれほど採用が難しいのかについて詳しい理由を解説します。
人材不足が深刻化している
建設業界全体で人手不足が年々深刻化しています。施工管理や技術者の確保でさえ困難な状況の中、営業職に回せる人材はさらに限られてしまいます。
特に若い世代にとって、リフォーム業界は「ハードな仕事」というイメージが根強く、選ばれにくい職種です。そのため、採用活動を行っても応募数自体が少なく、限られた人材を業界全体で取り合う状態になっています。結果として、人材不足が慢性化し、採用の難しさが一層際立っているのです。
若手が敬遠する業務内容
リフォーム営業は、机の上だけで完結する仕事ではありません。お客様のご自宅を訪問して状況を確認したり、現場で職人と調整をしたりと、体を動かす仕事は多く発生します。また、成果が出るまでには一定の時間がかかるため、「すぐに結果を出したい」と考える若者にとってはモチベーションを保ちにくい面があります。
その結果、就職・転職市場では「体力的にも精神的にも大変そう」「自分には続けられないかも」と思われ、応募を敬遠されがちです。仕事内容に対するこうした誤解や不安を解消しない限り、若手の応募を増やすのは難しいでしょう。
労働条件や業界イメージの悪さ
「残業が多い」「休みが少ない」——リフォーム業界にはそんなイメージがつきまとっています。国土交通省の調査によれば、建設業では月に4日以下しか休めない人が約6割に上るというデータもあり、求職者にとって「働きづらい業界」という印象が強いのです。
もちろん、すべての会社がそうとは限りません。しかし、業界全体のイメージが先行してしまうため、改善を進めている企業であっても「どうせどこも同じ」と思われてしまいがちです。特にワークライフバランスを重視する若い世代にとっては、このイメージが応募をためらう大きな理由になっています。
営業と施工を併任させられる負荷
多くのリフォーム会社では、「営業が契約を取り、工事の管理まで行う」という兼任体制であることが少なくありません。
確かに、顧客との関係構築から工事完了までを一貫して担当できるのは大きなやりがいの一つです。しかし同時に、業務負担が非常に大きくなり、「思っていた以上に大変だ」と感じる社員が少なくありません。特に未経験で入社した人にとっては、知識を身につけながら二重の役割を果たすことになり、負担感が大きな離職理由になってしまいます。
採用力を高めるための募集手法と媒体の選び方
採用活動でまず大切なのは「母集団形成」、つまり応募者の母数をしっかりと確保することです。どんなに面接や教育体制に力を入れても、応募がなければ採用自体が成り立ちません。そのためには、自社が求める人材に合わせて「どの媒体を使うか」「どんな見せ方をするか」を考える必要があります。
採用手法ごとに特徴や強みは異なり、どのチャネルを選ぶかによって結果は大きく変わります。ここでは代表的な手法を紹介しながら、媒体の選び方や活用のポイントを詳しくご紹介します。
求人サイトの活用
求人サイトはもっとも一般的で、幅広い層に情報を届けられる手段です。建設業に特化した求人サイトもあれば、総合的な転職サイトもあり、それぞれ閲覧者の層が異なります。
掲載するときは「どんな人に来てほしいのか」を意識しながら情報を作り込むことが大切です。たとえば「施工管理経験者歓迎」「資格取得支援制度あり」など、ターゲットが応募したくなるような要素を明記することで、経験者層の応募意欲を高められます。
また、給与や休日数などの条件を曖昧にせず、正直かつ具体的に記載することも重要です。求職者は複数社を比較するため、情報のわかりやすさが応募の決め手になるケースは少なくありません。
SNSを使った情報発信
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSは、企業の雰囲気や日常を自然に伝えられる場です。求人情報だけでなく、現場で働く社員の声や、日々の仕事風景を写真や動画で発信することで、応募者に「ここなら自分も働けそう」とイメージしてもらいやすくなります。
SNSの最大の強みは拡散性です。フォロワーを介して自社の情報がどんどん広がるため、広告費をかけずに認知度を高めることも可能です。特に「未経験者や異業種からの転職希望者」にリーチしやすいのが特徴です。
ただし、SNS採用は一度発信して終わりではなく、継続的に情報を更新していく必要があります。更新が途絶えてしまうと「活動していない会社なのかな?」という印象を与えてしまうこともあるため、運用体制を整えたうえで取り組むことが成功のポイントです。
社員紹介(リファラル)制度
リファラル採用は、社員のつながりを活用して新しい人材を紹介してもらう方法です。紹介者は会社の雰囲気や実情を知っているため、マッチング度が高く、入社後の定着率も良い傾向があります。
特に建設業のように人間関係やネットワークが強い業界では効果が出やすい手法です。紹介者に対しては「紹介成功でインセンティブ支給」といった仕組みを導入すると、社内の協力体制も得やすくなります。
ただし、リファラル採用は数に限りがあるため、それだけで採用をまかなうのは難しいのが現実です。他の媒体と組み合わせて使うことで、効果を最大化できます。
大学・専門学校との連携
中長期的な採用戦略として有効なのが、教育機関とのつながりを持つことです。建設や建築分野を学んでいる学生にインターンシップを提供したり、学内で説明会を実施したりすることで、早い段階から自社に興味を持ってもらうことができます。
特に「資格取得支援」や「入社後のキャリアパス」を明確に示すと、学生にとっては安心材料になり、応募意欲の向上につながります。学内に出す求人票でも「どんなサポート体制があるのか」を具体的に記載すると、他社との差別化になります。
この方法は即効性よりも、数年先を見据えた採用基盤づくりに効果的です。人材不足が慢性化しているリフォーム業界だからこそ、若手を育てる視点でのアプローチが重要になります。
「辞められない営業マン」を作る組織文化と育成制度
せっかく採用した人材がすぐに辞めてしまう…。これはリフォーム業界でよく聞く悩みです。とくに営業職は成果が出るまで時間がかかるため、最初の数か月をどうサポートするかが定着率を大きく左右します。
そこで大切になるのが、入社後の育成制度や評価の仕組み、そして働きやすい環境づくりです。この3つが揃えば、営業マンは「これなら続けられる」と感じ、長期的に活躍してくれるのです。
ここでは「辞められない営業マン」を育てるための具体的なポイントをご紹介します。
段階的な教育制度で「一人前」になるまでをサポートする
リフォーム営業は、商品や工事方法の知識、見積もりの作り方、営業トークなど覚えることが山ほどあります。最初からすべてをこなすのは無理があるため、会社側が「ステップを分けて成長を支える仕組み」を用意してあげることが大切です。
例:
・新人研修:社会人マナーや基本的な建築知識を学ぶ
・先輩同行:現場調査やお客様訪問を一緒に体験する
・部分的な実践:商談の一部だけ担当し、徐々に役割を広げる
上記のような流れで育成すれば、自分でも「成長できている」と実感しやすくなります。また、資格取得の支援や外部研修の補助などを導入すれば、本人のスキルアップ意欲も高まり、会社への信頼感も強まります。
「一人前になるまで会社が見てくれている」という安心感が、辞めにくさにつながります。
メンター制度で「孤立しない環境」をつくる
新人が早期に辞めてしまう大きな理由のひとつが「相談できる人がいないこと」です。営業は外回りが多く、社内で顔を合わせる時間も限られるため、孤立感を抱きやすい仕事です。
そこで有効なのが、先輩社員が日常的にフォローするメンター制度です。営業のノウハウだけでなく、ちょっとした疑問や悩みを気軽に聞ける存在がいるだけで安心感は大きく変わります。「売上がすぐに上がらなくても、会社は見捨てない」というメッセージを伝えることが、新人を支える大きな力になります。
また、OJT(現場での実地研修)をメンターが兼任する形にすれば、教える側も育ち、社内の結束力も高まります。
公正で多角的な評価・報酬制度を導入する
営業マンが辞めてしまうもう一つの大きな理由は「評価が契約件数や売上だけで決まってしまうこと」です。数字がすべてだと、不公平感やプレッシャーから心が折れてしまいます。
そこで大切なのは、多角的な評価基準を設けることです。
・契約件数や売上額(成果)
・顧客アンケートや満足度(サービスの質)
・チームへの貢献度(協調性・後輩指導など)
・新しい知識や資格の習得(成長度)
このように複数の視点で評価することで「数字がすべてではない」と伝えられます。
また、上司と部下が定期的に1on1ミーティングを行い、キャリアの希望や悩みを話し合うことで、社員は「ちゃんと自分を見てもらえている」と感じられます。評価制度は単なる査定の仕組みではなく、「社員を育てる仕組み」だと考えることが大切です。
働きやすさを重視した組織文化づくり
最後に忘れてはいけないのが「働き方そのものの改善」です。どれだけ育成制度を整えても、残業ばかりで休みが取れない環境では、長く続けるのは難しいでしょう。
リフォーム営業の現場で効果が期待できるのは、以下のような取り組みです。
・残業削減:ITツールで日報や見積を効率化し、早く帰れる仕組みをつくる
・有給休暇の取得促進:チームで案件を分担し、誰かが休んでも回る体制にする
・属人化の解消:案件をチーム共有し、個人だけに負担が集中しないようにする
社員が「この会社なら長く働ける」と感じられれば、定着率はもちろん、求人募集のときの魅力にもつながります。
結局のところ、「人材育成」と「働き方改善」をセットで考えることが、辞められない営業マンをつくる一番の近道なのです。
営業手法の工夫で採用の“説得力”をアップさせるポイント
営業マンを採用するとき、応募者が一番気にしているのは「この会社で自分も成果を出せるのか?」ということです。だからこそ、採用活動の中で「この会社なら安心して働ける」と感じてもらうことが大切です。
ここでは、営業手法を活かして採用力を高めるための具体的なポイントをご紹介します。
画像や映像を利用して「わかりやすさ」を伝える
未経験の人が実際の現場を具体的にイメージするのは難しいものです。そんなときに効果的なのが、実際の現地調査の映像や工事前後の施工動画を活用する方法です。
たとえば、ドローンで撮影をした施工前や施工後の映像を見せると、リフォームの成果が視覚的に伝わり「自分が提案する価値」を実感できます。
またこうした最新ツールを導入していること自体が、「この会社は時代に合った営業をしている」と応募者に安心感を与えます。結果的に「ここなら自分でも営業ができそうだ」と思えるわけです。
見積や施工事例の透明性をアピールする
営業で一番大切なのは「お客様に誠実であること」です。これはお客様に対してだけでなく、応募者に対しても同じです。
採用活動では、以下のような姿勢を伝えると効果的です。
・見積書の内訳を細かく開示する
「なぜこの金額になるのか」をお客様に説明できる会社は、応募者にとっても安心材料になります。
・成功事例だけでなく、失敗から学んだ改善事例も共有する
「うまくいかなかったことも正直に話す会社なんだ」と信頼感が増します。
・契約から施工完了までの流れをオープンに見せる
全体像を理解できれば、応募者は「自分がどの場面で活躍できるのか」を想像しやすくなります。
営業の透明性を強調することで、応募者は「ここならお客様から信頼される営業ができる」と前向きな気持ちになれるのです。
営業プロセスを見える化して「誰でも成果を出せる」体制を示す
応募者が一番不安に思うのは、「自分に営業ができるのか?」という点です。だからこそ、営業の流れを会社として仕組み化し、未経験でも成果を出せる環境があるということを示すことが大切です。
例:
・営業のステップをマニュアル化し、誰でも同じ流れで提案できるようにする
・提案書や資料、システムを整備して、説明しやすい環境を用意する
・先輩社員が同行して、最初の商談はチームでフォローする
こうした体制を伝えることで、応募者は「自分一人で頑張らなくてもいいんだ」と安心できます。「未経験でも成果を出せる仕組み」があることを可視化することは、採用の大きな説得力になるのです。
成功事例やチーム営業で「入社後のイメージ」を持たせる
採用活動で強力な武器になるのが、成功事例を具体的に伝えることです。たとえば、「未経験で入社した社員が半年で初契約を獲得した話」や「先輩とチームで営業を成功させた事例」を紹介すると、応募者は「自分もこうやって成長できるんだ」と未来を描けるようになります。
また、営業はどうしても「個人プレー」というイメージを持たれがちですが、チームでフォローし合う文化があることを伝えるのも重要です。「困ったときに相談できる仲間がいる」「案件はチームで動かすから孤立しない」といった体制を説明すれば、応募者は安心して挑戦できると感じます。
こうして入社後の成功イメージを明確に持たせることが、応募者のモチベーションを高め、採用の説得力をアップさせるポイントになります。
未経験者採用vs経験者採用、それぞれの戦略とメリット・デメリット
人材採用において大きなテーマとなるのが、「未経験者を採用して育てるか」「経験者を採用して即戦力として活かすか」という選択です。どちらが正解というわけではなく、会社の現状や目指す方向性によって最適な方法は変わってきます。
ここでは、それぞれのメリット・デメリットと採用戦略をわかりやすく解説します。
未経験者採用のメリット・デメリットと戦略
メリット
未経験者の採用は、何よりも「伸びしろの大きさ」が魅力です。業界の常識にとらわれていないため、自社のやり方を素直に吸収しやすく、会社の文化に馴染みやすい傾向があります。
また、モチベーションが高い人材が多く、成長意欲を刺激すればぐんぐん力をつけていきます。給与も経験者に比べて抑えめにスタートできるため、長期的に育てることでコストパフォーマンスの良い戦力になってくれる可能性があります。
デメリット
一方で、育成コストがかかるのは避けられません。研修やOJT、メンター制度といった仕組みを整える必要があり、教育に時間もお金も投資することになります。
また、営業や施工管理といった専門職では成果が出るまでに時間がかかるため、短期間で即戦力を求める場合には不向きです。
戦略ポイント
未経験者採用を成功させるには、「安心して学べる環境」をつくることが最大のポイントです。基礎から段階的に学べる研修や、いつでも相談できるメンター制度を導入し、不安を解消しながら成長を後押ししましょう。
また、「小さな成功体験」を積ませる工夫も大切です。たとえば、商談の一部を担当させて成果を感じさせる、行動量や努力を評価に反映するなど、途中経過をしっかり認めることで早期離職を防ぎ、前向きに成長できる人材に育ちます。
経験者採用のメリット・デメリットと戦略
メリット
経験者を採用する最大の強みは「即戦力になること」です。業界の知識や営業スキルをすでに持っているため、入社後すぐに成果を期待できます。場合によっては顧客基盤や独自のノウハウを持ち込み、会社全体の売上や営業力の底上げにつながることもあります。
さらに、既存社員にとって良い刺激になるのも大きなメリットです。新しい手法や現場での経験を共有することで、チーム全体のスキル向上に貢献してくれます。
デメリット
ただし、経験者は条件面での要求が高くなりがちです。高い給与や役職を求められることも多く、会社として待遇をどう調整するかが課題となります。
また、自分なりのやり方が身についている人ほど、新しい環境に馴染みにくいこともあります。場合によっては、前職とのやり方の違いに違和感を覚え、ミスマッチにつながるリスクもあります。
戦略ポイント
経験者採用をスムーズに進めるためには、事前に条件を明確にしておくことが重要です。給与やポジションについてお互いの期待値を調整し、入社後のトラブルを防ぎましょう。
また、せっかくの経験を活かすためには、すぐに力を発揮できる業務フローやサポート体制を整えておくことも大切です。そのうえで、チームへの馴染みを意識したマネジメントを行い、組織文化への順応を後押しすることで、長く活躍してもらえるようになります。
採用プロセスの運用で見落としがちなポイント
応募者が「ここで働きたい」と思うかどうかは、給与や待遇だけでなく、採用プロセスの進め方そのものにも大きく影響します。
面接や書類選考にばかり目が行きがちですが、実はちょっとした運用の差が応募者の印象を左右し、最終的な入社の決め手になることも少なくありません。
ここでは、採用の現場で見落とされやすい大切なポイントを解説します。
応募から内定までのスピード感を意識する
採用で失敗しがちな典型例のひとつが「対応の遅さ」です。応募から面接までに数週間かかる、面接後の結果連絡がなかなか来ない、条件提示が遅れる――こうした状況では、せっかくの有望な人材も待ちきれずに他社へ流れてしまいます。
特に、優秀な人材ほど複数社から声がかかっているため、スピード感は採用成功のカギになります。書類選考や面接日程はできるだけ早く調整し、面接後は数日以内に評価・連絡を行うのが理想です。内定通知もタイミングを逃さず行い、条件や入社日も明確に伝えると応募者は安心できます。
迅速な対応は「この会社は自分を大切に考えてくれている」という好印象を与えることにつながります。採用のスピード感は、そのまま応募者にとっての会社の誠実さを映す鏡だと考えると良いでしょう。
待遇や福利厚生の提示
応募者がまず知りたいのは「自分はどのような条件で働けるのか」という点です。そのため、給与や各種手当だけでなく、福利厚生や働きやすさも含めて、できる限りわかりやすく伝えることが大切です。
例えば、基本給やインセンティブの仕組み、残業代の有無、有給休暇の取得状況、産休・育休の制度などを具体的に示すと、応募者は安心して検討できます。求人票や説明資料に「よくある質問」形式で整理するのも効果的です。
条件が曖昧なままだと「入社してから聞いていた話と違うのでは」と不安を招きます。逆に、丁寧に提示されていれば「この会社は信頼できる」と感じてもらえるでしょう。
仕事内容やキャリアパスを具体的に伝える
応募者が最も気にしているのは「実際にどんな仕事をするのか」「どんな成長が見込めるのか」です。そのため、仕事内容や担当範囲を具体例を交えて説明することが大切です。
例えば、営業職なら「新規顧客の開拓と既存顧客のフォローが半々」「入社半年で小規模案件を担当し、1年後には大規模案件に挑戦」など、イメージできる形で伝えると安心感につながります。
また、昇進のステップやスキルアップの研修制度を示すと「ここでキャリアを積めばこう成長できる」と未来を描きやすくなります。加えて、チーム体制やサポート環境を伝えることで「自分一人で頑張るのではない」という安心感を与えることもできます。
離職理由や不安を事前にヒアリングする
採用面接というと「こちらが評価する場」と思われがちですが、実は応募者の本音を聞き出す場でもあります。過去の離職理由やキャリアの不安を丁寧に聞き取っておくことは、入社後の定着率を高めるうえで非常に効果的です。
例えば「前職では残業が多くて体力的にきつかった」「成長のチャンスが少なかった」などの理由が分かれば、入社後の配属やサポート体制に活かすことができます。そのため、面接やカジュアル面談の場で、応募者が安心して話せる雰囲気をつくることが大切です。
こうしたヒアリングを通じて「この会社は自分のことを理解してくれる」という信頼感が生まれ、入社の決め手にもなります。また事前にリスクを把握できるので、早期離職を防ぐことにもつながります。
給与・待遇以外で応募者に響く“付加価値”の提供アイデア
応募者が会社を選ぶとき、必ずしも給与や基本的な待遇だけを見ているわけではありません。特にリフォーム業界のように現場での対応力や専門スキルが求められる仕事では、「働きやすさ」「成長できる環境」「会社の雰囲気」といった要素が大きな魅力になります。
ここでは、給与以外で応募者の心を動かす“付加価値”の提供アイデアをご紹介します。
柔軟な働き方でライフスタイルに寄り添う
働き方の柔軟さは、応募者にとって大きな安心材料です。例えば、フレックスタイム制を導入すれば「朝は子どもの送り迎えをしてから出社できる」「夕方に早めに退社して家族と過ごせる」といった生活スタイルに合わせた働き方が可能になります。また、リモートでできる業務を在宅で対応できるようにすれば、移動時間を減らして効率的に働ける点も魅力です。
こうした制度は特に子育て世代や副業を希望する人にとって「この会社なら長く働けそう」と思わせる大きな要因になります。柔軟な働き方は単なる福利厚生ではなく、応募者のライフスタイルを尊重する姿勢を示す“会社の価値観”そのものでもあります。
資格取得やスキルアップ支援で成長意欲を刺激する
応募者が必ず抱く「この会社で自分は成長できるだろうか?」という問いに応えるのが、資格取得支援やスキルアップの仕組みです。例えば、資格試験の受験料を会社が負担したり、外部講座や研修への参加費を補助したりする取り組みは、応募者にとって大きな安心感と魅力になります。
さらに、資格を取得した社員にキャリアアップの機会や資格手当を用意すれば「努力がしっかり報われる会社」というイメージが強まります。こうした仕組みは、未経験者や若手応募者にとって「ここで頑張れば未来が開ける」と感じさせ、入社後のモチベーションにもつながります。
安全教育や福利厚生で安心感を提供する
現場で働く社員にとって、安全に仕事ができる環境は何より大切です。定期的な安全研修や現場での教育を実施している会社は、それだけで応募者に安心感を与えます。また、健康診断や労働保険などの基本的な制度に加えて、社員旅行やレクリエーションなど交流の機会を設けることも効果的です。
「安心して働ける職場かどうか」は入社後の定着率に直結します。単に福利厚生が整っているだけでなく、「仲間と一緒に頑張れる環境」「会社が自分の健康や安全を守ってくれる」という実感を持てることが、応募者にとって強い魅力になります。
社内の雰囲気や企業ミッションを伝える
応募者が入社を決めるとき、意外と大きな要素になるのが「会社の雰囲気」や「理念」です。どんなに条件が良くても、社内の雰囲気が合わなければ働きたいとは思えません。だからこそ、社員同士の協力体制や日常の雰囲気をわかりやすく伝えることが大切です。
また、会社の理念やミッション、地域への貢献活動などを打ち出すことで「この会社で働くことに意味がある」と感じてもらいやすくなります。さらに、実際に働く社員の声や体験談を紹介すれば「ここなら自分もやっていけそうだ」と応募者が具体的にイメージできます。
給与や待遇はもちろん大切ですが、それ以上に「ここで働きたい」と思わせる雰囲気や文化を伝えられるかどうかが、最終的な入社の決め手になるのです。
成功事例:採用→定着→成果につながった企業の取り組み
リフォーム業界では、「採用してもすぐ辞めてしまう」「なかなか定着しない」と悩む会社も少なくありません。しかし、採用の仕方や育成の仕組みを工夫することで、長期的に活躍できる人材を育てることは可能です。
ここでは、実際に成果を上げている企業の取り組みを紹介します。
採用戦略の工夫でミスマッチを防ぐ
あるリフォーム会社では、中途採用を中心に人材を確保していますが、単に給与や待遇を並べるのではなく、求人票の中で「会社のミッション」や「仕事の社会的意義」をしっかり打ち出しています。
例えば、「地域の住まいを安全で快適に保つ」という目的を明確に伝えることで、応募者が「この会社で働く意味」を実感しやすくしています。
また、面接の前に必ず現場見学を行い、実際の雰囲気や社員の人柄を応募者に体感してもらう取り組みも導入しました。このプロセスによって「想像していた仕事内容と違った」というギャップを大幅に減らし、入社後の早期離職を防ぐことに成功しています。
結果として、応募者が安心して入社を決断できるようになり、採用の質と定着率の両方を向上させています。
入社後の育成とフォローで定着を支える
採用した人材を長く定着させるためには、入社後のサポートが不可欠です。ある会社では、配属先の上司が中心となって新入社員をフォローし、入社1〜3か月のタイミングで定期面談を実施。業務に対する不安や今後の希望をヒアリングし、必要に応じて配置換えや追加研修を行っています。
また、未経験者を採用した場合は、経験豊富な社員によるOJT(現場での指導)や、基本から学べる研修を充実させることで「自分でもやっていける」という自信を持たせています。
こうしたきめ細かなフォローの積み重ねによって、3年後の定着率が8割以上という高い成果を出しています。定着の裏には、「人を育てながら寄り添う姿勢」があるのです。
採用から定着、成果につながる仕組み
あるリフォーム会社では、「採用」と「育成・定着」を切り離さず、一つの流れとして設計しています。採用段階から「入社後にどんな仕事を任されるのか」「どんなキャリアが描けるのか」を明確に伝える一方で、入社後はフォロー体制を整え、社員が安心して働ける環境を構築しています。
こうした取り組みによって、入社後のモチベーションを維持しやすくなり、社員ひとりひとりの力を最大限に発揮できる環境が実現しました。その結果、売上や顧客満足度といった具体的な成果にもつながっています。
リフォーム業界は人材の確保が難しいと言われますが、このように「採用から定着、成果までを一体で考える」ことで、強い営業体制を築くことが可能になります。
まとめ|採用に困らない営業体制を築くためのステップ
リフォーム営業の採用で本当に大切なのは、「人を集めること」だけではありません。入社した社員をきちんと育て、長く働ける環境を整えることが成功のカギになります。
そのためには、まず自社の現状を整理することが大切です。どのポジションで人手が足りていないのか、採用活動や教育制度にどんな課題があるのかを明確にすることから始まります。
次に、採用の方法を一つに絞らず、幅を広げる工夫が必要です。求人媒体の使い分け、SNSの活用、社員紹介制度の導入などを組み合わせることで、より多くの応募者にアプローチできます。また、他社にはない営業手法や、ドローンなど最新技術を活用した取り組みを打ち出すことで、採用段階から会社の魅力を伝えられます。
そして、入社後は教育や評価の仕組みを整えることが大切です。研修やメンター制度で成長を後押しし、明確な評価基準を示すことで、モチベーションを保ちながら定着率を高めることができます。
ただし、すべてを一気に取り入れる必要はありません。まずは小さな一歩から始め、成果を確認しながら改善を重ねることがポイントです。
採用は一時的なイベントではなく、会社の未来を左右する「継続的な戦略」です。こうした取り組みを積み重ねていくことで、安定的に人材を確保できる、強い営業体制を築いていくことができるでしょう。








