「住まいを変え、笑顔を生み、お客様を幸せに」を企業理念に掲げ、太陽光発電システムやオール電化設備の施工・販売・メンテナンスなどを手がける株式会社トップライフ様。同社では、これまで直接屋根に上って実施していた太陽光パネルや屋根の点検作業に、DroneRoofer(ドローンルーファー)を導入しました。これによって点検の質の向上だけでなく、屋根に上ることへ抵抗がある人材や女性の採用力を強化することに成功しています。今回、同社でDroneRooferの導入を主導された泰地 幸雄様、実際にドローンによる点検作業を行う芳賀 憩様に導入の背景や実際の活用法、そして今後の展望についてお話を伺いました。
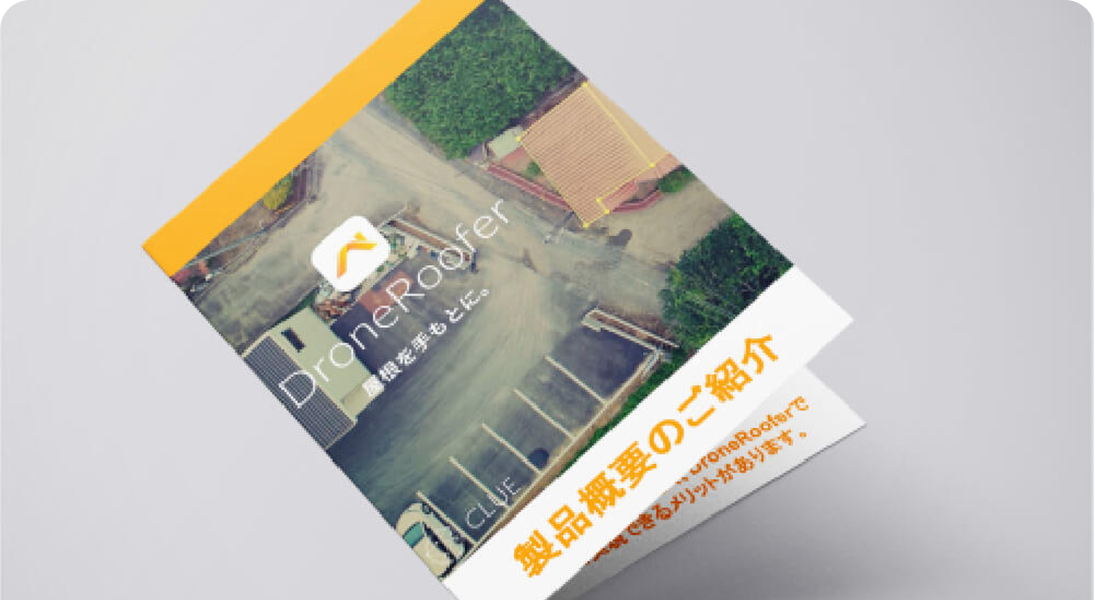
貴社の状況に合う適切な、
DroneRooferの活用方法がわかります。
- ・外装点検を誰でも、安全に実施したい
- ・積算や見積など提案準備を効率化したい
- ・リフォーム提案で他社と差別化したい
目次
年間の点検作業は1万件以上。持続的な顧客関係を軸にした独自のビジネスモデルとは
—— 事業概要についてお聞かせください。
泰地様:私たちトップライフは、北海道、九州を除く全国エリアで、太陽光発電システムやオール電化設備の施工・販売・メンテナンスを手がけています。加えて、住宅リフォーム事業やリノベーション事業も展開しており、環境に配慮したエネルギー活用と安心で快適な住環境づくりを支えることをミッションに掲げています。
同業他社との競合が激しい業界において、弊社では一期一会の関係では終わらない、ご縁をいただいたお客さまと継続的な関係性を築いていくこと、長期的な価値を提供し続けていくことを大切にしていることが特徴です。具体的には、太陽光発電システムや家庭用蓄電池、エコキュートといった設備の無料メンテナンスをきっかけとしてお客さまのご家庭を訪問し、そこで不具合が見つかればリフォームや工事をご提案する流れを取っています。
つまり、収益の主軸はリフォーム施工ではありますが、継続的なメンテナンスがあって初めて成り立つビジネスモデルです。ドローンの活用も、屋根に直接上がれない状況でも点検を可能にし、安定的にメンテナンスを実施できることを狙いとしています。
—— 太陽光パネルの点検作業について教えてください。
芳賀様:太陽光パネルの表面に割れや経年劣化がないか、配線が露出していないか、鳥の巣などの異物が付着していないかを確認します。屋根に登れる場合は直接確認し、登れない場合はドローンで撮影して判定するという流れです。
また作業全体では、太陽光パネルだけでなくエコキュートや蓄電池についても点検しており、水抜きや内部配管の接続部分からの漏水、配線の劣化、ネジの緩みといった項目までチェックしています。お客さまご自身の点検ですと説明書通りの判断が難しい部分ですので、専門知識を持った私たちが直接確認することが、お客さまの安心につながると考えています。
こうした点検作業は、すべての支店を合計すると年間で1万〜1万5千件ほど実施しています。単純に月平均にならすと、800〜1,000件ほどです。ドローンの活用は、私が在籍する東日本支社(関東支店)だけでなく、本社がある関西支店でも需要が高いと聞いています。この理由として、3階建て住宅が全国で最も多い地域であり、3階建ての住宅ははしごをかけても屋根に届かず、また敷地が狭いためにはしご自体が設置できないケースも少なくありません。
—— 東日本支社のカスタマーサポート体制について教えてください。
芳賀様:2025年現在は8名体制で、そのうち実際に現場に出向いてメンテナンスを行うのはうち5名です。男女比で言えば男性6名に対して女性が2名で、女性スタッフも現場に出て点検を行っています。大宮に拠点はありますが、千葉、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、神奈川と関東一円を対象にしており、月ごとの状況に応じてエリアを分担して担当しています。
現場作業に“100%の安全”は存在しない。顧客視点に立った、本質的な事故対策の重要性
—— 安全意識を根付かせるため、東日本支社ではどのような取り組みをされているのでしょうか?
芳賀様:前職は警察官として勤めており、業界未経験からの挑戦でした。入社後、すぐに実施されたのが安全に関する教育・研修です。たとえば、はしごをかける際には必ず固定してから上ることや、傾斜の強い屋根や高所は必ず二人一組で対応すること、危険と判断された場合は点検を後日に回してドローンで対応することなどが強く指導されました。研修全体は2ヶ月ほどで、そのうちおよそ3割の時間は作業の安全に関する教育に割かれていたと思います。
そうした研修期間の中で特に印象に残っているのが「私たちが怪我をすれば、一番迷惑を被るのはお客さま」という言葉です。お客さまに安心を提供するはずの点検にもかかわらず、作業時間といった弊社側の都合を優先して事故を起こしてしまえば本末転倒です。私たち自身が危険を避けることこそが、顧客視点に立った対応だと学びました。
—— ドローン活用の背景には、どのような課題があったのでしょうか?
泰地様:何よりも社員の安全を守りたいという思いから、ドローン導入の検討がスタートしています。屋根に上る作業は、どうしてもリスクを伴うもので、屋根の上での作業で「100%安全」を実現することは、ほとんど不可能なことです。
大掛かりな工事であれば足場を組んで安全を確保するのが一般的ですが、点検作業のためだけに数十万円の費用をかけて足場を設置するのは現実的ではありません。そのため、多くの現場でははしごで屋根に上って対応しますが、滑り止めを取り付けたり、下にマットを敷いたりといった対策には限界があります。
だからこそ重要なのは、事故の確率をいかに減らすかという視点です。特に屋根からの転落事故は人命に関わるため、本人だけでなくお客さまにとっても心理的な負担が大きく、絶対に避けなければなりません。点検作業の現場リスクを低減するため、そもそも事故の確率を低減できるドローン活用こそが、課題解決の最適解だと判断しました。
複雑な飛行申請や研修はドローン専門家におまかせ。「DroneRoofer」導入の決め手とは
—— 「DroneRoofer」を導入いただいた当時の狙いについてお聞かせください。
泰地様:自社でドローン機材を購入しての内製化や、操作経験のある人材を採用するという選択肢もあるとは思いますが、飛行許可の申請など複雑な部分もあるため、やはりドローン専門のプロに任せた方が確実だと判断しました。補助金制度の創設など、行政側でも民間のドローン活用を後押しする環境整備が進んでいたこともあり、複数のドローン専門のサービスを比較検証しました。
—— 「DroneRoofer」を導入いただいた決め手をお聞かせください。
泰地様:初回のオンライン商談の際に、サポート体制やドローン保険などの説明があり、しっかりしていると感じました。契約までの流れがスムーズで、オンライン商談後の1週間以内には来社いただき、デモ飛行をしていただきました。
こうしたスピード感に加え、担当してくださった方々が信頼できる人ばかりだったことも、安心できるポイントだったと思います。また、国交省への飛行許可の事前申請についても、点検作業の現場で簡単に申請できる仕組みが整っており、面倒な準備なく使える点は非常にありがたいと感じました。
最終的には支店長会議の場で、社長を含めた支店長以上の役職者に向けて「DroneRoofer」の導入についてプレゼンテーションを行いました。決して費用も安くはありませんし、ドローンがなくとも点検作業自体は可能です。しかし、万が一事故で社員が命を落とせば、社員本人だけの問題ではなく、お客さまや会社全体、そして社員の遺族にも多大な迷惑をかけてしまいます。このリスクを考慮してほしいと会議では伝え、結果として「DroneRoofer」導入の承認を得ることができました。
長はしごからの脱却で業務負担を軽減。女性・若手社員が積極的なドローン活用を後押し
—— 「DroneRoofer」の導入はどのように進んだのでしょうか?
泰地様:2022年に、まずドローン1台を関西支店に導入しました。当初は「本当に点検作業の現場で使えるのか」という検証の意味合いが強く、とりあえず本社周辺の点検作業で活用し始めています。
検証にあたって重視していたのが、ドローンの安全性や操作性に加えて、お客さまや近隣からの反応です。CLUE社の担当の方からは「近隣から覗き見と誤解されるリスクがあるかもしれない」との事前説明を受けていたのですが、実際に現場でクレームが入ることは一切なく、スムーズに運用を始められています。
その後は住宅の階数を問わず、ほぼ全件でドローンを活用していたこともあり、1か月で20〜30件とほぼ毎日のように飛ばしていました。従来の方法である長はしごは重さが20キロもあり、車のルーフキャリアから降ろして伸ばし、雨樋を潰さないよう注意して屋根にかけるといった手間がかかっていたのですが、ドローンであれば箱から取り出してプロペラを装着するだけで済むため、体力的にも効率面でも負担が軽減されています。
—— 関西支店以外への展開は、どのように進められましたか?
泰地様:関西における検証後、2ヶ月後には関西、関東、中部、北陸の各支店に計4台を配備しました。導入にあたり、CLUE社の担当の方にオンラインと現地の両方で研修していただいています。
「DroneRoofer」導入後の現場からは、「意外と簡単に操作できる」という感想が多かったですね。特別に旗振り役を置かずとも現場には自然と浸透し、若手を中心に活用が進みました。また、女性社員の増加もドローンの積極的な活用を後押ししています。
—— 普段の点検作業の流れを教えてください。
芳賀様:まず現場に到着したらお客さまにご挨拶し、当日の点検内容をご説明します。そのうえでスマートフォンから飛行申請を行い、承認を得てからドローンを組み立てて飛行させます。
iPadの画面に屋根の映像を映し出しながら、お客さまと一緒に太陽光パネルの状態を確認し、「今、割れや劣化がないかを見ています」「この程度の色あせなら問題ありませんね」と説明するという流れです。
1件あたりの点検時間は約2時間ですが、ドローンを使うのは15〜20分程度です。慣れてくるとドローンの方が長はしごよりも早く、効率的に作業できます。ドローンによる点検後は、屋根裏や床下、エコキュートの配管などを確認して、すべての作業が完了します。
女性採用の障壁を取り除き、人材力を強化。社員の安全と、点検の質の向上を同時に実現できた
—— 「DroneRoofer」に対する感想をお聞かせください。
芳賀様:研修後に初めてドローンを操作した際、最初は「ラジコンのようだ」と感じましたが、カメラのズーム機能の精度が想像よりも高く、無理に近づかなくても鮮明に確認できるのが印象的でしたね。私が操作する時に最も注意するのが電線やアンテナで、特にアンテナを支えるピアノ線のような細いワイヤーは見えにくく危険です。
また、最近では正面からの映像だけでなく、斜めの角度から撮影し、パネルと屋根の隙間に鳥の巣がないか確認するといった工夫もできるようになり、点検の質も高まっているように感じます。やはり言葉だけの説明よりも、写真や映像があることで説得力が増し、全体像を確認できる点は点検作業における付加価値となっています。こうした積み重ねがアップセルやクロスセルに結びついているのだと思います。
さらにお客さまから直接的な言及こそありませんが、最新の技術を使いこなして点検している姿は、信頼の獲得につながっているはずです。特にお子さまがいらっしゃるご家庭ですと、「一度ドローンを見てみたかった」と喜んでいただけることがあり、会話が自然と広がることも珍しくありません。
—— 「DroneRoofer」の導入によって、どのような成果が得られていますか?
芳賀様:一番大きな成果は、屋根に登れない社員でも点検業務に就けるようになったことです。私自身もそうですが、女性社員が入社してすぐにドローンを使って点検できる環境が整っていたことは本当に嬉しかったですね。長はしごによる点検作業は力仕事ですし、手順に慣れるまでに時間がかかります。
泰地様:弊社の採用活動においても、ドローンの活用はアピールポイントのひとつです。特に応募者が女性の場合には「ドローンを使っているので安全です」と説明しており、それが安心材料にもなっているようです。以前は女性からの応募があっても、弊社側の仕組みが整っていないことで見送ることもあったのですが、今は体制が整ったことで性別を問わず、適材適所で活躍できる人材を採用できています。
技術の活用と採用力の強化で新しいメンテナンスサービスを。中小企業こそ、ドローンを活用すべき
—— 今後の展望についてお聞かせください。
泰地様:現在、定額制の会員向けメンテナンスサービスの提供を検討しています。具体的には、お客さまが日常的には手が回らない排水管や雨樋の洗浄、エアコン内部のクリーニングなどを弊社で担っていけるようにしたいと考えています。
これまでのメンテナンスサービスは単発のため高額になりやすく、お客さまにとって費用面がネックでした。こうした課題を解決するため、定額制の仕組みによってもっと利用しやすくする方向で試行錯誤している段階です。もちろん、こうした新しいメンテナンスサービスにおいても点検作業は不可欠であり、そこでもしっかりドローンを活用していきたいですね。
芳賀様:私自身、まだまだドローンの距離感やカメラ角度の調整に慣れていない部分があり、もっと技術を磨いていきたいと思っています。たとえば、雨樋の汚れや壁の上部など、お客さまが普段目にすることのできない部分をドローンで鮮明に映し出し、一緒に確認できるようになれば、安心感をより高められると感じています。
また、今後後輩が入社してきた際には、最初から高い場所に上るのではなく「ドローンなら気軽に確認できる」と伝え、恐怖心なく業務に取り組めるように教えていきたいと思います。
—— ドローン導入を検討している企業に向けて、アドバイスをお願いします。
泰地様:高所作業が発生する企業であれば、最低1台は持っておくことを強くおすすめします。「DroneRoofer」によるドローン操作は手間が少なく、現場の負担を大きく減らしてくれるはずです。大企業であれば専任の運用担当を置いても良いでしょうし、中小企業であれば限られたリソースの中でも効率的に運用できます。決して安い投資ではありませんが、余計な手間が発生しない点を考えると、特に中小企業にこそ大きなメリットがあるのではないでしょうか。















