マイホームの快適性や省エネ性能を高めたいと考えるお客様は年々増加しています。しかし、リフォームは高額になりやすいため、費用面で不安を抱える方も多くいらっしゃいます。
そこで、リフォーム会社様としてぜひ注目していただきたいのが「リフォーム補助金」です。2025年も、国や自治体によってさまざまな支援制度が用意されており、条件を満たせばお客様のリフォーム費用を大幅に軽減できる可能性があります。
補助金情報を的確に把握し、お客様に分かりやすくご案内できることは、お客様からの信頼獲得や受注率アップ、単価向上にもつながる大きな強みとなります。
この記事では、2025年に活用できる主なリフォーム補助金の種類や申請方法、制度の活用メリットについて詳しくご紹介いたします。
補助金を活用した提案力を高めたいとお考えのリフォーム会社様の参考になれば幸いです。
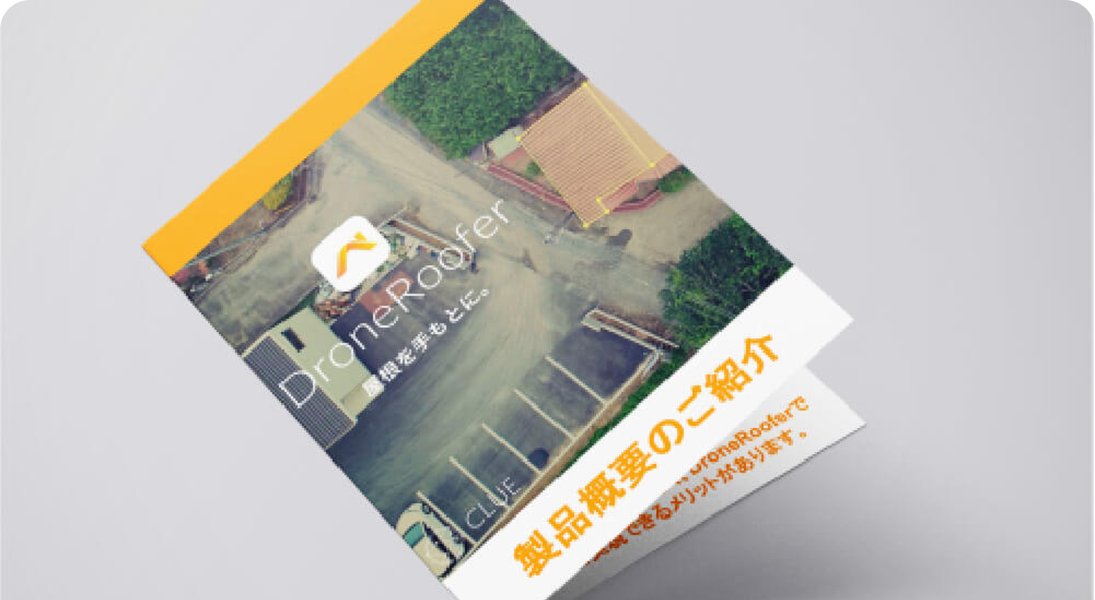
貴社の状況に合う適切な、 DroneRooferの活用方法がわかります。
- ・外装点検を誰でも、安全に実施したい
- ・積算や見積など提案準備を効率化したい
- ・リフォーム提案で他社と差別化したい
目次
リフォーム補助金とは?仕組みと目的
リフォーム補助金とは、国や自治体が住宅の性能向上や省エネ化、耐震化などを目的に、リフォーム工事の一部を支援する制度です。通常、リフォームは自己負担が大きくなりがちですが、補助金を活用することで実質的な負担を軽減できます。
ここでは、「仕組み」と「目的」について詳しく解説します。
リフォーム補助金の仕組み
リフォーム補助金は、対象となる工事を行うことで、かかった費用の一部が国や自治体から補助される制度です。
【仕組みのポイント】
・補助金対象となる工事が決まっている
→断熱改修やバリアフリー改修など、あらかじめ定められたリフォームのみ対象
・上限額や補助率がある
→工事費のすべてが補助されるわけではなく、「最大〇万円」「工事費の1/3」など条件付き
・登録事業者を通じて申請する場合が多い
→補助金制度に登録された事業者が代行するケースが主流
つまり、ただリフォームすれば補助金がもらえるというわけではなく、「対象工事」「申請条件」がそろってはじめて利用できる仕組みになっています。
リフォーム補助金の目的
リフォーム補助金には、国や自治体が取り組む社会的課題を解決する目的があります。主な目的は以下の通りです。
・省エネ推進
断熱材の設置や窓の二重化、高効率給湯器の導入などにより、エネルギー消費を抑制。CO2削減や光熱費の節約にもつながります。
・耐震性向上
耐震補強工事を支援することで、地震に強い安全な住まいを増やし、災害リスクを軽減します。
・子育て・高齢者支援
手すりの設置や段差解消などのバリアフリー改修、子育て世帯向けの快適な住環境づくりを後押し。暮らしの安全と安心を守ります。
・住宅の長寿命化
「長期優良住宅化」を目指すリフォームを推進することで、住宅の資産価値を維持し、空き家問題の解決にもつなげます。
リフォーム補助金は、単に「お得に工事できる制度」ではありません。
国や自治体にとっては、
・エネルギー問題の改善
・防災対策の推進
・少子高齢化社会への対応
・空き家や老朽住宅の減少
といった、社会的課題を解決するための重要な施策なのです。
つまり、補助金は「個人の暮らしの質を高める」と同時に「社会全体の課題解決」にも直結する制度と言えます。
国が提供する主なリフォーム補助金制度
リフォーム補助金には、国が予算を組んで実施している全国共通の制度があります。
対象となる工事は「省エネ」「耐震」「バリアフリー」「子育て支援」など目的ごとに分かれており、条件を満たすと補助金を受けることが可能です。
ただし、国の補助金は年度ごとの予算が決まっており、人気のある制度は早期終了してしまうこともあります。申請を検討している方は、早めに動くことが大切です。期間内でも予算が上限に達すると早期終了してしまいます。
ここでは、2025年に利用できる代表的な国のリフォーム補助金制度を6つご紹介します。
1.介護保険住宅改修(バリアフリー)
介護が必要な方の自立を支援するため、住宅のバリアフリー改修に使える制度です。
【対象者】
要介護または要支援の認定を受けている方
【補助対象工事の例】
・手すりの取り付け
・段差の解消(スロープ設置など)
・滑りにくい床材への変更
・引き戸や洋式便器への交換
【補助額】
上限18万円(工事費20万円の9割が上限)
【対象期間】
通年
高齢者の暮らしを安全・快適にするための心強い支援です。
2.先進的窓リノベ2025事業
住宅の窓を断熱性能の高いものに改修することで、省エネや光熱費削減をサポートする制度です。
【対象者】
登録された業者で工事を行う住宅の所有者
【補助対象工事の例】
・高断熱窓への交換
・内窓設置(二重サッシ化)
・外窓交換
・ドア交換(窓と同時工事の場合のみ)
【補助額】
最大200万円/戸
(※工事内容や窓の大きさで変動)
【申請受付期間】
2025年3月31日~2025年12月31日(予算に達し次第終了)
※2024年11月22日以降に対象工事に着手したものが対象
断熱性能を大きく向上させられるため、人気の高い補助制度のひとつです。
3.子育てグリーン住宅支援事業
従来の「こどもエコすまい支援事業」を引き継ぐ形で始まった制度です。子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、省エネ改修などに対して補助金が支給されます。
【対象者】
以下の1,2の両方を満たす方が対象となります。
1.登録事業者と契約してリフォーム工事を行う
2.リフォームする住宅の所有者等であること
【補助対象工事の例】
以下の必須工事から2つ以上
【必須工事】
・開口部の断熱改修
・外壁・屋根・天井または床の断熱改修
・エコ住宅設備の設置
【必須工事と合わせてできる工事例】
・子育て対応改修(食洗機・宅配ボックスなど)
・防災性向上改修(防犯安全ガラスへの交換)
・バリアフリー改修(手すり設置、段差解消など)
【補助額】
最大40万円~60万円/戸(条件に応じて最大上限額が変動する)
【申請受付期間】
2025年3月31日~2025年12月31日(予算上限に達し次第終了)
※2024年11月22日以降に対象工事に着手したものが対象
子育て世帯の「快適でエコな住まいづくり」を後押ししてくれる制度です。
4.給湯省エネ2025事業
給湯器を省エネ性能の高いタイプに交換すると補助される制度です。
【対象者】
以下の3つの条件に当てはまる人が申請対象となります。
1.「給湯省エネ事業者」と契約し、以下の2つのいずれかの方法で高効率給湯器(対象器)を導入する
・リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法
・既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅(戸建てまたは共同住宅等)を、購入する方
2.対象機器を設置する住宅の所有者等である
3.建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅
【補助額(基本額)】
・エネファーム(家庭用燃料電池):16万円/台
・ハイブリッド給湯器:8万円/台
・エコキュート(ヒートポンプ給湯器):6万円/台
※戸建てが最大2台、共同住宅は最大1台まで
【申請受付期間】
2025年3月31日~2025年12月31日(予算に達し次第終了)
※2024年11月22日以降に対象工事に着手したものが対象
光熱費が気になる方にとって、導入の後押しになる制度です。
5.既存住宅における断熱リフォーム支援事業
築年数が経過した住宅を対象に、断熱性を高めるリフォームを支援します。
【対象】
居住用の住宅(賃貸も可、店舗兼用住宅は不可)
【補助対象工事の例】
・高性能断熱材や窓・ガラスを使った全面改修(トータル断熱)
・居間だけの部分的な断熱改修(居間だけ断熱)
【補助額】
・戸建て住宅:最大120万円/戸
・集合住宅:最大15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は最大20万円)
【公募期間】
2025年9月2日~2025年12月12日
「冬は寒く、夏は暑い」と感じる既存住宅におすすめの補助制度です。
6.長期優良住宅化リフォーム推進事業
住宅の耐震性や省エネ性を高め、長く安心して住める家にするための補助制度です。
【対象者】
施工業者を通じて申請。工事前にインスペクション(住宅診断)が必要
【補助対象工事の例】
・耐震補強・省エネ改修・劣化対策など
・三世代同居や子育て対応リフォーム
・災害に備える改修工事など
【補助額】
リフォーム後の住宅性能によって異なる。
・評価基準型:最大80万円/戸(特定条件で最大130万円/戸)
・認定長期優良住宅型:最大160万円/戸(特定条件で210万円/戸)
(特定条件:三世代同居対応改修工事、若者・子育て世帯の改修工事、既存住宅の購入者の改修工事の場合)
【対象期間】
住宅登録期間(リフォームする住宅の所有者や所在地等を登録すること。工事を始める前に登録する必要あり):2025年5月20日~2025年12月12日
【Ⅰ期】
認定長期優良住宅型
<戸建住宅>2025年5月30日~2025年9月30日
<共同住宅>2025年6月13日~2025年9月30日
評価基準型
<戸建住宅>2025年6月13日~2025年9月30日
<共同住宅>2025年6月27日~2025年9月30日
【Ⅱ期】
2025年10月上旬~2025年12月22日
大規模なリフォームや性能向上リフォームを検討している家庭に特にメリットが大きい制度です。
自治体ごとに異なるリフォーム補助金の実態と特徴
国の補助金制度に加えて、多くの自治体でも独自のリフォーム補助金が用意されています。
耐震改修や断熱リフォーム、バリアフリー工事など、地域の課題や住民ニーズに合わせた支援が多いのが特徴です。
ここでは、自治体補助金の実態と特徴について詳しく解説します。
自治体リフォーム補助金の実態
自治体の補助金は、以下のような工事に幅広く対応しています。
・耐震診断・耐震改修:大地震に備えるための住宅強化
・断熱リフォーム:窓や外壁の断熱化による省エネ性能向上
・バリアフリー工事:手すり設置や段差解消など高齢者・障碍者に配慮した改修
・省エネ設備導入:太陽光発電や高効率給湯器の導入
補助率や上限額は自治体によって異なる
国の制度とは違い、自治体補助金は地域ごとに条件や金額がバラバラです。上限額が5万円程度の軽微な支援から100万円を超える大型補助までさまざまな補助制度があります。
また、地域経済の活性化を目的として「地元施工業者に依頼した場合のみ補助対象」となる制度もあります。5万円〜10万円程度の補助が支給されるなど、利用者にとっても費用負担が軽くなる嬉しい制度です。
自治体リフォーム補助金の特徴
自治体の制度は、地域特有の課題を解決する目的で設定されています。
例:
・東京都:耐震改修や省エネ設備導入への補助が充実
・大阪市:高齢者の暮らしを守るため、バリアフリー改修を重点的に支援
・地方自治体(移住・定住支援):空き家を活用して移住者がリフォームする場合、費用の一部を助成
国の補助金と自治体の補助金を組み合わせることで、自己負担を大幅に減らせるケースもあります。
例:
・国の「断熱リフォーム補助金」+自治体の「省エネ改修補助」
・国の「バリアフリー改修支援」+自治体の「高齢者住宅改修助成」
リフォームを検討する際は、国の制度と合わせて必ずお住いの自治体の補助金制度を確認することが大切です。自治体の公式サイトや相談窓口で最新の情報をチェックして、最適な制度を活用しましょう。
リフォーム補助金の申請手順と注意点
リフォーム補助金を利用する際は、「工事の前か後か」「誰が申請するのか」が制度ごとに大きく異なります。
ここでは、主要な補助制度ごとに申請手順・必要書類・注意点を解説します。
1.子育てグリーン住宅支援事業・先進的窓リノベ事業・給湯省エネ事業
・申請のタイミング:工事の完了・引き渡し後
・申請者:施工する事業者
【申請の流れ】
1.各事業に登録されている施工業者を探す
2.施工事業者と契約を結ぶ
3.工事実施し、完了報告を行う
4.引き渡し
5.施工事業者が必要書類をまとめ、補助金を申請
【必要なもの】
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・住民票(世帯票)
・既存住宅の不動産売買契約書 など
【注意点】
・登録事業者でないと申請できないため、事前に必ず確認が必要
・予算枠にかぎりがあるため、早めの申し込みが推奨される
2.既存住宅における断熱リフォーム支援事業
・申請のタイミング:工事着工前
・申請者:対象住宅に常時居住している所有者、または所有予定者
【申請の流れ】
1.公募期間中に公式HPから申請様式をダウンロード
2.必要書類を作成
3.電子メールおよび郵送で提出
・交付申請書
・暴力団排除に関する誓約事項
・総括表
・明細書
・その他必要書類(PDF保存も必要)
【必要なもの】
住宅区分により異なる
【注意点】
・公募期間が決まっているため、期限を過ぎると申請できない
・書類の不備があると審査に時間がかかり、交付が遅れる
3.長期優良住宅化リフォーム補助金
・申請のタイミング:工事着工前
・申請者:施工業者
【申請の流れ】
1.施工業者が事業者ポータルサイトや支援室HPから申請書式を入手
2.書類を作成・提出
3.承認後に工事開始
【必要なもの】
・工事計画書
・見積書
・設計図面 など
【注意点】
・事業者登録をしていない施工業者では申請不可
・長期優良住宅の基準を満たす内容でなければ補助対象にならない
4.介護保険住宅改修(バリアフリー)
・申請のタイミング:工事着工前
・申請者:介護保険の被保険者本人
【申請の流れ】
1.ケアマネージャーなどに住宅改修について相談
2.「住宅改修が必要な理由」を作成
3.支給申請書類を保険者(市町村)に提出
4.承認後に工事実施
【必要なもの】
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの
【注意点】
・事前申請が必須。承認前に工事を始めると補助対象外になる
・原則として20万円までの工事が上限(自己負担1割~3割あり)
5.自治体のリフォーム関連助成金
・申請のタイミング:制度により異なる(事前申請が多い)
・申請者:制度により異なる(施主本人か施工業者)
【注意点】
・自治体によって内容が大きく異なるため、必ず公式HPや窓口で確認をすること
・募集期間が短い場合もあり、締め切りを過ぎると利用不可
・一部地域では条件が設定されていることがある
(例:子育て世帯や移住世帯のみ対象)
補助金と併用可能な制度・減税もチェックしよう
リフォーム補助金は、単体で利用するだけなく、自治体の補助金や減税制度と組み合わせて使うことで負担をさらに軽減できる場合があります。
ここでは主な併用パターンをご紹介します。
補助金同士の併用
・国の補助金+自治体の補助金
例えば、国の「先進的窓リノベ事業」で窓の断熱改修を行い、同時に自治体の断熱リフォーム補助金を活用できるケースがあります。
ただし、同じ工事内容に対して二重で補助を受けることは不可のため、対象工事を分けるか、制度の規約を確認する必要があります。
減税制度との併用
リフォームに関する減税制度には、以下のような種類があります。
【所得税の控除】
・耐震リフォーム減税
・省エネリフォーム減税
・バリアフリーリフォーム減税
これらは組み合わせて適用できる場合が多いのが特徴です。
【固定資産税の減税】
省エネや耐震リフォームを行った場合、一定期間、固定資産税が減額される制度があります。所得税減税と固定資産税減税を同時に受けることも可能です。
補助金だけでなく減税制度も組み合わせることで、実質的な負担をさらに軽くできます。
注意点
制度によっては「他の補助制度との併用不可」と明記されている場合もあるため、必ず事前に確認しましょう。
また、減税制度を受けるには、確定申告が必要になることが多いです。
まとめ|補助金を賢く利用してリフォーム費用を抑えよう
2025年も、省エネ化や耐震性の向上、子育て・高齢者支援などを目的とした補助金制度が豊富にあります。特に「子育てグリーン住宅支援事業」や「長期優良住宅化リフォーム推進事業」などは、条件を満たせば数十万円〜数百万円規模の補助が見込め、お客様にとって実質的な負担が大きく軽くなる可能性があります。
ただし、補助金には予算枠や申請期限、対象工事や登録業者の条件などに加え、制度内容が年度途中で変更される可能性もあります。そのため、情報は常に最新のものを確認し、国や自治体の公式サイトなど信頼できる情報源を参照することが不可欠です。
施工前の打ち合わせ段階から制度の適用可否を確認し、地域の補助制度や減税制度も含めて最適な提案ができる体制を整えておくことで、無理のない費用で理想の住まいを提案でき、顧客の満足度・信頼性・受注率のいずれも向上するでしょう。








