2025年4月、建築基準法の改正がされました。
「どんな工事で確認申請が必要になるのか」「既存不適格や再建築不可物件はどう扱われるのか」など、リフォーム会社にとっては見逃せないポイントが盛りだくさんです。法律を正しく理解していないと、思わぬトラブルや営業機会の損失につながる可能性もあります。
逆に言えば、この法改正を正しく押さえられれば、「法令遵守に強い、安心して任せられる会社」として顧客から選ばれる大きなチャンスにもなります。
この記事では、2025年建築基準法改正の概要や、工事別の確認申請の要否、会社経営へのメリット・デメリット、さらに営業戦略への活かし方まで分かりやすく解説します。
「これからどう対応していけばいいのか」と悩む方に向けて、実務に役立つヒントをお届けします。
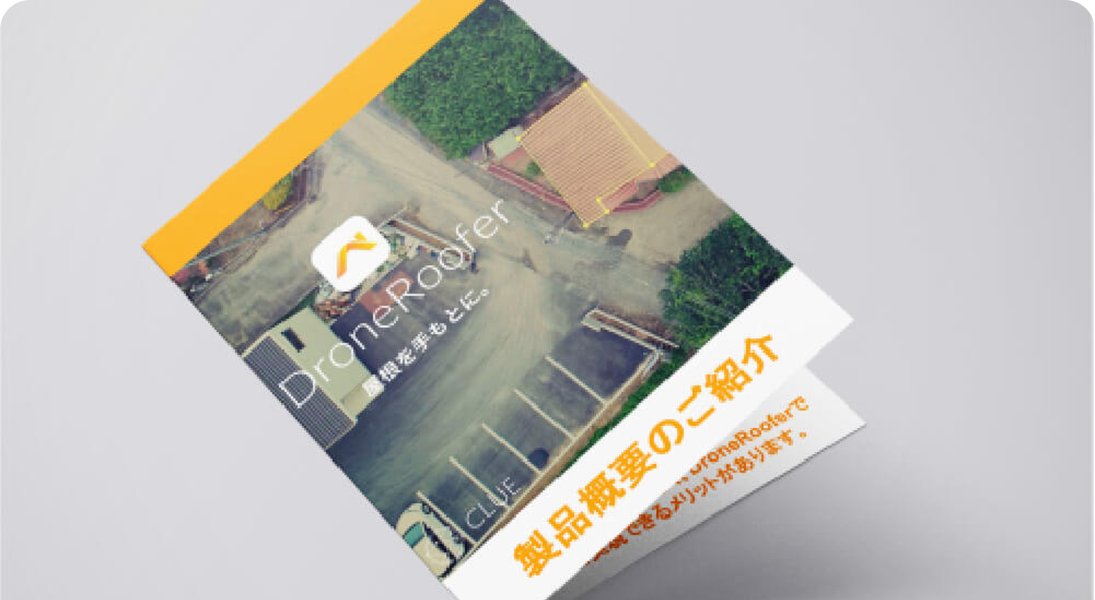
貴社の状況に合う適切な、 DroneRooferの活用方法がわかります。
- ・外装点検を誰でも、安全に実施したい
- ・積算や見積など提案準備を効率化したい
- ・リフォーム提案で他社と差別化したい
目次
2025年建築基準法改正とは何か?リフォーム会社が知るべき概要
2025年4月に施行された建築基準法の改正は、リフォーム業界にとって大きな転換点となりました。これまで「新築工事」に重点が置かれていた建築確認申請のルールが、既存住宅のリフォームにも適用されるようになったからです。
特に、木造2階建て住宅といった最も身近な戸建て住宅に関わる改正点が多く、リフォーム会社としては「どの工事に確認申請が必要か」を判断する力がこれまで以上に求められます。
ここでは、改正で大きく変わった3つのポイントを整理していきます。
4号特例の縮小
これまで「4号特例」によって、木造2階建て住宅や延べ面積200㎡以下の平屋建ては、一部のリフォームで確認申請が不要とされていました。しかし、今回の改正により、この特例の範囲が大きく縮小されました。
「木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)」はこれまで通り申請が不要ですが、「木造2階建て」や「木造平屋建て(延べ面積200㎡超)」は、確認申請が必須になります。
つまり、これまで「小規模だから」「2階建てでも申請は不要だから」と見なされていた工事でも、法改正後は確認申請の対象となる可能性が高まったのです。リフォーム会社にとっては、従来の感覚で判断すると違反リスクを抱えることになりかねません。
新しい「新2号建築物」制度
改正後は、従来の「4号建築物」は廃止され、そのうち新たに確認申請が必要となったものが「新2号建築物」の中に位置づけられました。これがリフォーム業界にとっては非常に重要なポイントです。
「新2号建築物」は、主に木造2階建て住宅など、最も一般的な戸建て住宅が含まれるカテゴリーです。つまり、リフォーム案件の多くがこの新しい区分に該当することになります。
リフォーム会社にとっては「自分たちが扱う住宅が新2号建築物に入るかどうか」を見極めることが、今後の工事対応の基本となります。これまで「4号建築物だから大丈夫」と考えていた判断基準が通用しなくなるため、意識の切り替えが欠かせません。
主要構造部の修繕・模様替えに申請が必要
今回の改正で大きな注目点となっているのが、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)に関わる工事です。これらを「半分以上」修繕・模様替えする場合は、大規模な工事とみなされ、確認申請が義務化されます。
屋根や階段の工事は、従来は「リフォームの範囲」として捉えられ、確認申請を意識する場面は少なかったかもしれません。しかし、改正後は工事内容によっては申請が必須となるため、従来の常識で判断することはできなくなっています。
リフォーム会社は「主要構造部に関わる工事かどうか」「改修の規模がどの程度か」という視点で、申請の要否を慎重に確認することが求められます。
どのリフォーム工事で確認申請が必要になるか(ケース別)
ここでは、新たに「新2号建築物」に該当する建物が、どのようなケースで確認申請が必要になるのかを見ていきましょう。
特に「主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)」に関わる工事や、用途変更、増築などは要注意です。
ここでは、実際の現場でよくあるケースを挙げながら申請が必要になる工事について詳しく解説します。
主要構造部を50%以上改修する場合
最も典型的なのが、主要構造部を半分以上改修する工事です。壁・柱・床・梁・屋根・階段といった建物を支える部分を過半数まとめてやり直すと「大規模修繕・模様替え」となり、確認申請が義務化されます。
例:
・築40年以上の木造住宅をフルリノベーションし、柱や梁をまとめて補強する
・屋根の葺き替えで、下地や垂木まで入れ替える
・階段を既存のものから完全に掛け替える
これまで「リフォームの延長」として扱われていた工事も、改正後は「確認申請が必要な大規模改修」として扱われます。フルリノベーション案件では特に注意が必要です。
耐震補強工事
地震対策のための耐震補強も、主要構造部に手を加える場合は原則として確認申請が必要になります。建物の安全性に直結するため、行政のチェックが必須です。
例:
・壁を抜いて筋交いや耐力壁を新設する
・柱や梁に金物を追加し補強する
・床下で土台や大引きを補強する
耐震リフォームは住宅の価値を高める工事として需要が増えていますが、基準に適合しないと申請が下りない可能性もあります。早い段階で設計者や確認検査機関に相談しておくのが安心です。
断熱改修・省エネ改修
近年ニーズが高まっている断熱や省エネリフォームも、規模によっては申請が必要です。特に外壁や屋根を大規模に改修する場合は要注意。
例:
・外壁をすべて張り替えて断熱材を入れ直す
・窓やサッシを建物全体で入れ替え、外皮性能を一新する
・屋根全体を葺き替え、省エネ仕様に変更する
窓を数か所二重サッシに替えるなどの小規模工事は不要ですが、建物全体の断熱性能に関わる工事は「主要構造部の改修」と見なされることがあります。そのため、工事規模を見極めることが大切です。
用途変更を伴うリフォーム
住宅を店舗や事務所に改装するなど、用途を変更する場合にも確認申請が必要になります。
例:
・1階の居住スペースを飲食店に改装する
・住宅の一部を賃貸用事務所にする
・倉庫をアトリエやスタジオとして活用する
用途が変わると、採光や換気、避難経路、防火性能など、新しい用途に応じた基準をクリアしなければなりません。特に飲食店や福祉施設などは基準が厳しいため、設計段階から確認しておく必要があります。
増築工事
床面積が10㎡を超える増築は、従来どおり確認申請が必須です。
例:
・2階に部屋を増やす
・平屋に新しい部屋を継ぎ足す
・10㎡を超えるサンルームを設置する
特に、都市部では防火地域や準防火地域に該当することも多いため、増築工事では耐火性能の基準を満たすことも忘れてはいけません。
確認申請が不要なリフォーム
一方で、建物の安全性に大きな影響を与えないリフォームは、これまで通り確認申請が不要です。
例:
・キッチン、トイレ、浴室の交換
・手すりやスロープの設置(バリアフリー化)
・構造上重要でない間仕切壁の撤去・設置
ただし「申請不要=完全に自由にできる」というわけではありません。たとえ申請が不要でも、工事後の建物が建築基準法に適合していることは必須です。違反が発覚すると是正を求められる可能性もあるため、基本的な法令遵守の意識は常に持っておきましょう。
再建築不可物件と既存不適格建築物の法的扱い―2025年法改正でどう変わるか
2025年4月の建築基準法改正では、再建築不可物件や既存不適格建築物に対する取り扱いに関しても、これまで以上に慎重になる必要があります。
とくに「どの程度の改修なら認められるか」「確認申請が通るかどうか」といった部分で、以前より厳しくチェックされるケースが増えているのです。リフォーム会社としては、早い段階でリスクを見極め、顧客に分かりやすく説明できることが信用につながります。
ここでは、それぞれの扱いと改正による具体的な変化について詳しく解説します。
再建築不可物件とは
「再建築不可物件」とは、建築基準法の接道義務を満たさない土地に建つ建物のことです。具体的には、幅4m以上の道路に2m以上接していない敷地にある建物が該当します。災害時に避難や消防活動が難しくなるため、新築や大規模な改築が認められません。
よくある例として以下のようなものがあります。
・路地奥にある長屋や袋小路の住宅
・戦前に建築された狭小地の建物
これらは老朽化しても建て替えができず、維持管理の負担が大きいのが特徴です。さらに融資が通りにくいため売却も難しい、という実務上のデメリットもあります。
そのため「壊して建て直す」ではなく、「既存の建物を直して使う」方向でのリフォームが現実的な選択肢となるケースが多いのです。
既存不適格建築物の扱い
一方で、既存不適格建築物とは、建築当時は合法だったものの、法改正によって現在の基準に適合しなくなった建物を指します。
2025年の法改正では、既存不適格建築物に対しては緩和措置が整理されました。
・小規模な改修:申請不要、または緩和対象になる場合がある
・大規模な改修:現行基準に合わせることが求められる
つまり、ある程度のリフォームはやりやすくなった一方で、大掛かりな工事では基準適合が必須になるという二面性があるわけです。
実務では「どこまでが緩和対象か」をしっかりと理解したうえで、設計・申請を進めることが欠かせません。
改正で厳しくなったポイント
今回の法改正で注意すべきは、「新2号建築物」の創設です。
これにより、木造2階建て住宅や延床200㎡超の木造平屋などが、耐震性や省エネ性能に関する審査の対象となります。
そのため、次のような工事では確認申請が必要となります。特に、確認申請が通りにくい再建築不可物件や、現行基準に合わせることが求められる既存不適格建築物を対象とする場合では注意が必要です。
・主要構造部(柱・梁・壁・床・屋根・階段)を過半にわたり大規模に改修・交換するリフォーム
・接道義務を満たさない敷地での大規模な耐震補強や増改築
・建物全体の外皮(断熱・窓等)を大規模に改修し、同時に構造部に手を加える工事
ただし、屋根や外壁の表層を替えるカバー工法などは、国の通達で申請が不要とされるケースもあります。工事方法の選び方次第で対応可能な場合があるため、計画段階での見極めが重要です。
法改正後の円滑なリフォーム工事のためのチェックポイント
厳格化された法規制の中で、リフォーム工事を円滑に進めるために、実務上押さえておきたいポイントを解説します。
1.早めの現地調査とスクリーニング
工事の話が具体化する前に、現地を丁寧に調査しておくことが大切です。
接道状況や既存図面の有無、建物の構造状態を最初に把握することで、「この工事は確認申請が必要になるかもしれない」と早い段階で見極めができます。
例えば、接道義務を満たしていない場合や、構造部に大きく手を加える可能性がある場合は、後で手戻りが発生しやすい典型例です。調査結果を顧客に共有し、「ここにリスクがあるので、進め方を一緒に考えましょう」と事前に説明しておくと信頼関係を築きやすくなります。
2.壊さない設計での代替案
大規模な構造変更を伴うと申請が必要になりますが、「壊さない設計」を取り入れることで回避できる場合があります。
例えば、外壁を全て撤去せずにカバー工法で仕上げる、柱を抜かずに部分的な補強で対応するなどです。
全面改修よりもコストを抑えつつ、顧客に「法律上も手続きが簡略化できる」というメリットを提示できれば、契約につながりやすくなります。工法選びそのものを差別化の武器にすることができます。
3.工事を段階的に進める
一度に大規模な工事を行うと申請の対象になりやすいですが、工事を段階的に分けて進めるという方法があります。
例えば、まずは耐震性を確保する補修工事だけを行い、その後、断熱や内装のリフォームを追加する流れです。
顧客にとっても「資金を分散できる」「生活に合わせて改修を進められる」という利点があり、長期的な信頼関係にもつながります。
4.43条但し書きの活用
接道義務を満たさない物件は「再建築不可」とされることがありますが、必ずしも大規模な改修ができないわけではありません。
建築基準法43条の但し書きにより、審査会の許可を得れば例外的に建築や大規模な改修が可能になる場合があります。
ただし、手続きには時間や費用がかかり、自治体によって基準が異なる点に注意が必要です。顧客には「すぐに工事できるとは限らない」と伝えたうえで、早い段階から行政との協議を進めるのが賢明です。
5.行政や検査機関との事前協議
「この工事は申請が必要かどうか分からない」というグレーなケースは少なくありません。そんなとき自己判断で進めてしまうと、後から「やっぱり申請が必要だった」となるリスクがあります。
そのため、行政や確認検査機関に早めに相談し、見解をもらっておくことが大切です。事前に協議しておけば、審査に通りやすくなり、顧客にも安心して契約してもらえます。「調べておきました」と一言添えるだけでも、プロとしての信頼度が高まります。
法改正によるメリット・デメリット―会社視点での影響分析
2025年の建築基準法改正は、リフォーム会社にとって大きな節目となります。確かに手間や負担が増える場面もありますが、同時に「信頼される会社」として差別化できる絶好のチャンスでもあります。
ここでは、会社視点でのメリットとデメリットを詳しく解説します。
メリット
法改正の一番のメリットは、リフォーム業界全体で「法令遵守」がより強く意識されるようになったことです。今までグレーだった部分がはっきり線引きされることで、ルールを守る会社がより評価される時代に変わりつつあります。
「安心して任せられる業者を選びたい」というのは、顧客にとって一番の本音。法改正によってその目線がさらに厳しくなるため、きちんと対応できる会社ほど「選ばれる理由」を持てるようになります。
また、省エネ改修や耐震補強といった、これからの暮らしに直結する工事の需要が高まることも大きなポイントです。補助金制度と連動した動きも多いため、顧客にとっても「やる意味があるリフォーム」となり、受注のチャンスが広がります。
つまり、法改正は単なる規制ではなく、「会社の信頼性を高め、新規案件獲得のきっかけ」になり得るのです。
デメリット
一方で、現場にとっての負担は確実に増えます。確認申請が必要になる工事が増えたため、申請書類の準備や審査にかかる時間が追加されます。結果として工期が延び、顧客とのスケジュール調整が難しくなる場面も増えるでしょう。
また、コスト面でも影響があります。申請手数料や設計士への依頼費用などが発生するため、「思ったよりリフォーム費用が高くなった」と顧客に感じさせてしまう可能性があります。価格競争が厳しい中小のリフォーム会社にとっては、経営的な負担になりかねません。
さらに、違反工事に対する罰則が強化されたことで、これまで「つい見落とした」「以前は大丈夫だった」で済んでいたものが、今後は重大なリスクに直結します。体制が不十分な会社ほど、行政からの指摘やトラブルの可能性が高まります。
つまり、「対応を怠れば一気にリスクが拡大する」というのがデメリットの本質です。
注意点とリスク―違反しないために絶対に押さえる法律項目
リフォームは「既存の家を直すだけだから法律は関係ない」と思われがちですが、実際には多くの法律が関わっています。建築基準法をはじめ、都市計画法や消防法、省エネや耐震基準、接道義務など、見落としてしまうと工事後に「違反です」と指摘されるリスクもあります。
ここでは、リフォーム会社が特に注意しておきたい法律項目を整理してご紹介します。
都市計画法
リフォームは建物の中だけでなく、敷地の条件によっても制限を受けます。都市計画法では「建ぺい率(敷地面積に対する建物の立てられる割合)」や「容積率(延床面積の上限)」が定められており、これを超えて増築することはできません。
例えば、「もう一部屋増やしたい」と考えても、容積率オーバーなら許可が下りないこともあるということです。特に中古住宅を購入してからリフォームを考えるケースなどでは、土地の制約を事前に確認しておくことが重要です。
消防法・防火規制
リフォーム内容によっては、消防法も関わってきます。建物の規模に応じて、消火器や火災検知器の設置が義務付けられているケースがあり、特にマンションや店舗兼住宅のリフォームでは、必ずチェックが必要です。
また、防火地域や準防火地域に指定されているエリアでは、外壁や窓の仕様にも厳しい制限があります。ただ外壁を張り替えるだけのつもりが、防火基準に合う材料を選ばなければならない、というケースも少なくありません。知らずに工事を進めると、やり直しや追加コストが発生してしまう可能性があります。
省エネ・耐震基準
ここ数年で特に重視されるようになったのが、省エネと耐震性能です。断熱材や窓の性能は、省エネ基準を満たさなければ補助金や優遇措置を受けられない場合があります。逆に言えば、基準を意識すれば補助金をうまく活用できるというメリットもあります。
また、耐震についても、柱や梁を動かすような大きな間取り変更では注意が必要です。構造上の安全性を損なう工事は許されないため、建築士に相談して設計段階からしっかり検討することが大切です。
接道義務
接道義務も重要です。建築基準法では、建物は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないとされています。
特に古い住宅地では道幅が狭く、この条件を満たしていないケースもあります。その場合は増築や建て替えに制限がかかることがあり、「思う通りの工事ができない」という事態になりかねません。
マンション特有の規制
戸建て住宅と違い、マンションにはマンション特有のルールがあります。リフォームできるのは「専有部分」だけで、配管や外壁といった「共用部分」には手を加えられません。
また、管理規約や使用細則で「工事可能な時間帯」「床材の遮音性能」など細かい条件が決められていることも多いです。事前に管理組合へ相談していないと、工事中にストップがかかるケースも。マンションの場合は、法規制と同時に管理規約の確認が必須と言えます。
営業戦略として法律遵守をアピールする方法
リフォーム業界では、法改正にきちんと対応しているかどうかが、顧客にとっての安心感につながります。ただ「守っています」と言うだけでは伝わりにくいので、営業の中で分かりやすく示す工夫が大切です。
ここでは、信頼につながる具体的なアピール方法をご紹介します。
見積書や提案書に「法改正対応」を明示する
顧客にとって、見積書や提案書は最初に手にする大事な資料です。そこに「2025年の建築基準法改正に準拠した内容です」などと一言添えるだけで、安心感はぐっと高まります。
また、省エネや耐震に関する基準をクリアしている場合は、その内容を具体的に記載するのも効果的です。単に金額や工期を提示するだけでなく、「ルールを守った安心の工事」であることを可視化することが信頼につながります。
広告や説明で誤解を生まない表現を選ぶ
チラシやホームページで「安心・安全」とうたう会社は多いですが、それだけでは漠然としています。例えば「建築基準法に基づいた耐震補強工事」「最新の省エネ基準に適合」など、法律に即した表現を使うことで具体性が出て、他社との差別化にもつながります。
ただし、過度な誇張や誤解を招く表現は逆効果になるため注意が必要です。広告では「守っていることを正しく伝える」姿勢が重要です。
写真や書類を活用して「透明性」を示す
言葉だけでなく、写真や書類で「見える化」するのも強力なアピール方法です。例えば、確認申請書の控えや検査の様子を写真で残し、顧客に共有すれば「この会社はきちんと手続きをしている」と一目で伝わります。
また、工事の進捗や完了後の報告書に「法改正に基づくチェック項目」を盛り込むのも効果的です。透明性を打ち出すことで、顧客の信頼は確実に高まります。
ドローンなどを活用した最新技術での法対応と差別化
近年は、ドローンや3Dスキャンなどの最新技術をリフォームに取り入れる会社が増えています。単に作業効率を上げるだけでなく、法令対応の精度を高めたり、顧客に「見える安心」を届けたりできるのが大きなポイントです。
ここでは、その具体的な活用方法をご紹介します。
ドローンで屋根・外壁の現況を正確に把握
従来は足場を組んで目視するしかなかった屋根や高所の外壁も、ドローンを使えば短時間で高精度の調査が可能になります。
例えば、劣化の度合いや破損箇所をドローンで撮影し、その画像を建築確認申請の資料に添付することで、客観的な判断材料として活用できます。顧客にとっても「実際の映像」を見ながら説明を受けられるため、納得感が大きく変わります。
写真・動画で作業範囲を「見える化」
工事内容が抽象的だと、顧客は「どこまで直すの?」「本当に必要なの?」と不安になりがちです。そこで、ドローンや高精度カメラで撮影した写真や動画を使い、「補修が必要な箇所」「交換する部材」などを具体的に示すと、提案の説得力が格段にアップします。
施工前・施工中・施工後を記録して共有すれば、透明性の高いサービスとして信頼も得やすくなります。
活用技術そのものが他社との差別化ポイントに
最新技術を積極的に取り入れている姿勢そのものが、他社との差別化につながります。「この会社は新しい取り組みをしている」「安心できそう」と顧客に感じてもらえるのは大きな強みです。
また、省エネや耐震の改修工事でも3Dスキャンやシミュレーションを使えば、性能向上の効果を数値やイメージで示すことが可能です。こうした工夫は法令対応の裏付けになるだけでなく、顧客満足度アップにも直結します。
まとめ|法改正後も安心して営業できる体制づくりのステップ
2025年の建築基準法改正は、リフォーム業界にとって“単なるルール変更”ではなく、大きな節目となる出来事です。確認申請が必要な工事の範囲が広がり、既存不適格の扱いも変わることで、これまでのやり方では対応しきれないケースも出てきます。そのため、事前にしっかりと準備しておくことが、これからも顧客に選ばれる会社であり続けるためのカギとなります。
対応のステップはシンプルです。まずは、改正内容を正しく理解し、会社全体で共通認識を持つこと。そのうえで、申請や確認作業にスムーズに対応できる体制を整え、現場と事務が連携しやすい仕組みをつくること。そして最後に、法律をきちんと守っている姿勢を顧客にわかりやすく伝え、安心感と信頼を提供することです。
これらをひとつひとつ丁寧に積み重ねていけば、「規制が増えてやりにくい」ではなく「信頼を得るチャンスが広がった」と捉えられるはずです。法改正への対応を自社の強みに変えることで、価格だけではない価値を評価してもらえる営業基盤を築けるでしょう。
法改正はリスクではなく、未来への一歩です。“選ばれる会社”として安心して営業できる体制を整えていきましょう。








